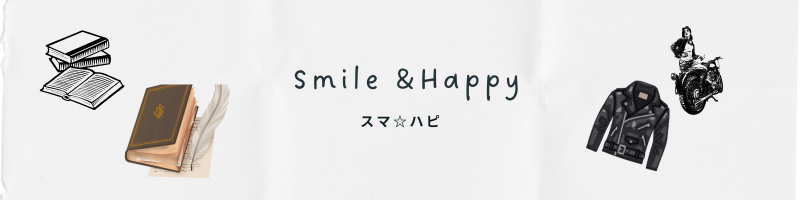笑顔で過ごせてますか?スマ☆ハピです!
当ブログに来ていだだきありがとうございます!
MotoGPを観ていると「どうしてV型4気筒のマシンばかりが速いんだろう?」と思ったことはありませんか?
直線での伸びやコーナー立ち上がりの加速力には、ちゃんと理由があるんです。
V4はエンジンをコンパクトに収められることでマシン全体のバランスが取りやすく、さらに点火タイミングを工夫してトラクションを生み出すことも可能です。
一方で、並列4気筒にもコーナリングでの扱いやすさという魅力があります。
この記事では、両者の違いをわかりやすく整理して、丁寧に解説します。
結論と全体像 — V4が速いのは“設計の総合力”が理由です.

結論からお伝えします。
MotoGPではV型4気筒(V4)が並列4気筒に比べて総合的に速くなることが多いです。
理由はひとつではなく、エンジンのコンパクトさ、回転部の損失の少なさ、そしてトルクや点火の“出し方”を自由に設計できる点が組み合わさるからです。
実際のデータでも、V4搭載マシンは短期間で高い勝率やトップスピードの記録を多く残しています。
最高速度の公式記録は366.1km/hに達したこともあり、これは現代GPマシンの“実力”を示す数字です。
パッケージングと重量集中 — 「短いから強い」は本当!?

V4は“前後の長さが短い”ため、マシン全体の設計で有利になります。
理由は単純です。
V字に配置するとシリンダー列が短くなり、クランクシャフトも短くできます。
短いクランクはねじれや振動に強く、支持するベアリング数を減らせるため、内部の摩擦やロスが低くなります。
これによりエンジンを車体中央に寄せやすく、重心をまとめることができます。
結果として直線加速やブレーキングからの立ち上がりで有利になります。
一方で、並列4はクランクが長めになりやすく、その分“慣性”が出て、コーナーで扱いやすい特性を生みます。
つまり、V4は直線と加速、並列4は扱いやすさ(コーナリング)で一長一短です。
クランクシャフトと摩擦 — “ロス”の差

V4はクランクの短さとメインベアリング数の少なさで、内部ロスを減らしやすい。
理由をもう少し分かりやすく言うと、クランクシャフトは回るたびにねじれや振動を受けます。
長いクランクはその影響を受けやすく、支持するベアリングも増えます。
支持が多いと摺動部分が増え、摩擦で失う力が増えます。
技術解説では、V4は短いクランクでメインベアリングを少なくできるため摩擦損失が減り、出力向上に寄与すると説明されています。
具体的な“差”はチューニングや回転数で変わりますが、実戦では数馬力〜十馬力クラスの有利さが競争力に直結しています。
これがトップレベルでの速さに響いています。
点火配列(ビッグバン)とトラクション — 地面を掴む工夫

V4は点火配列やクランク設計で“路面との掛かり方”を細かく作れるため、トラクションを稼ぎやすい。
理由をかいつまむと、すべてのパワーを“均等に”出すのではなく、ある瞬間にまとまって出す(=ビッグバン的な配列)ことが可能です。
こうするとリヤタイヤが一度トルクを受けてから休み、グリップを回復して次の瞬間に再び強く加速できます。
つまり滑らせにくく、加速でタイヤをより有効に使えるのです。
実戦面の例です。
近年のMotoGPでは360km/h台の最高速が複数回記録され、メーカーや週末によっては366.1km/hまで届いています。
直線での伸びは、V4の高回転域と空力・吸気設計が合わさった成果でもありますね。
デメリット/なぜ全メーカーがV4にしないのか?そして今後の規則

V4は強みが大きい一方で、扱いにくさや整備面の課題があり、全メーカーが一斉に移行するとは限りません。
理由は明快です。
短く軽いクランクはメリットですが、回転の慣性が小さいため“薄く滑る”とバイクが敏感に反応します。
つまり、ライダーやサスペンション、電子制御との相性が重要になります。
並列4は“安定感”やコーナリングのしやすさでライダーに好まれる特徴があります。
これがメーカーの選択理由の一つです。
また、技術面だけでなくレギュレーションの変化も影響します。将来の規則(例:排気量や空力規制の見直し)
次第では、エンジン選択の有利不利が変わる可能性があります。
チームやメーカーはその先を見据えて設計方針を決めています。
まとめ

1. 車体設計の自由度
- V4は前後に短いので、エンジンをフレームの中でコンパクトに収めやすい。
→ ホイールベースを最適化でき、マスの集中化(重心をコンパクトにまとめる)が可能。 - 並列4気筒は全長が長くなるため、フロントとリヤの重量配分やスイングアーム長に制約が出やすい。
結果:V4は「曲がる・加速する・止まる」の全てをバランス良くまとめやすい。
2. エンジン特性(トルクの出方)
- V4は爆発間隔を工夫しやすく、「ビッグバン点火」などトラクションを稼げる点火方式が使える。
→ リヤタイヤが滑りにくく、加速時にしっかり路面を掴む。 - 並列4気筒は高回転での伸びは良いが、トルクの立ち上がりがピーキーになりやすい。
結果:V4は「立ち上がり加速」で優位に立ちやすい。
3. 空力とエアインテーク
- V4は中央に吸気ダクトを配置しやすく、効率的にラムエアを取り込める。
- 並列4はシリンダーが横に並ぶため、どうしてもスペースが窮屈になりがち。
結果:V4は高速域でよりパワーを発揮しやすい。
4. 実際のMotoGPでの傾向
- V4勢(ドゥカティ、ホンダ、KTM、アプリリア) → 直線スピードと加速力が強い。
- 並列4勢(ヤマハ(2025年第16戦サンマリノGP投入、スズキ※撤退) → コーナリング性能は高いが、ストレートで不利。
実際、ここ数年のMotoGPではドゥカティのV4が圧倒的なストレートスピードを誇っています。
エンジン形式は「速さの設計図」です。
でも、それはフレームや電子制御、ライダーの好みとセットで初めて力を発揮します。
MotoGPの“速さ”は、技術の積み重ねと細かな調整の結果です。
今回はエンジン特性についてお話しました。
みんなの興味があれば、今後もMotoGPに関しての疑問をやさしく解説していきますね。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
共に楽しいバイクライフを送りましょうね!
この記事が良かったよって方はシェアして下さいね!
みんなでバイクライフをエンジョイしましょう!
次回もお楽しみに!